
ライトやサイクルコンピューター、そして電子制御サスペンションに電動シフト。自転車には多くの電子機器が取り付けられている。だがこれらの電子機器はすべてスタンドアロンで動作しており、機能がダブっているものも少なくない。例えば、自転車用ナビと盗難防止装置はどちらもGPSを利用するが、それぞれが独自のGPSシステムを搭載している。バッテリーもそうだ。デバイス毎に、個々のバッテリーを内蔵しているのが実態だ。

注:画像は(かなり大げさな)イメージ図です
こんな人は、いない…。
これらをすっきりとまとめられないかという試みが「OpenBike」プロジェクト。自転車の世界に、コンピューターの世界における「プラグアンドプレイ(PnP)」に近い概念を導入するものだ。
PnPとは、Windows 95で登場した概念。PCに周辺デバイスを接続する際に、利用者側が何もしなくても、デバイスの組み込みが自動的に行われる仕組みだ。USBメモリーやマウスなどがコンピューターのUSBコネクタに挿入されるだけで動作を始めるのは、このPnPのおかげと言える。
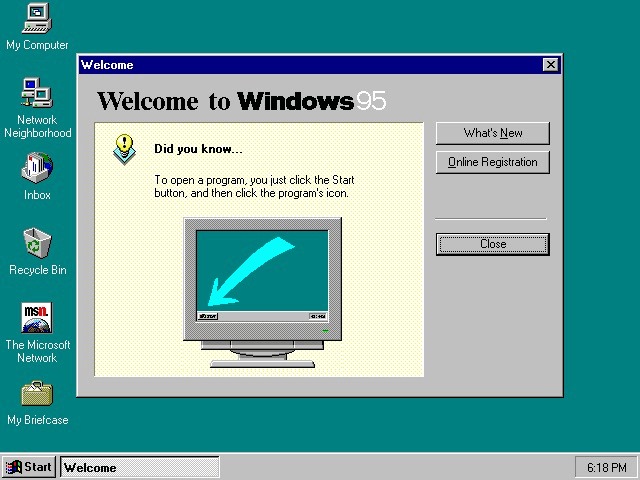
当時は誤動作も多く「Plug and Pray(挿して、祈れ!)」とも言われた
「OpenBike」では、自転車メーカー側は「OpenBike」の規格に準じた“プラットフォーム”を組み込んで販売する。具体的には、ペダルを漕いで充電するセンターバッテリーや、その電力をユーザーデバイスに供給するためのUSBポートなどだ。

サイクリストがこのプラットフォームに対応した自転車用アクセサリーを購入すれば、両者の間では「PnP」に近いことが行われ、取り付けやその後の利用が簡単になる。これが「OpenBike」の概念だ。
例えば、方向指示器やブレーキランプなどの取り付け作業が簡略化される。現在は、これらのアクセサリーの取り付けでは、ブレーキにセンサーを手作業で組み込まなければならない。だが「OpenBike」対応自転車にはセンサーが組み込まれているので、「PnP」で簡単に取り付けが可能だ。これによって方向指示器やブレーキランプを搭載する人が増え、自転車の安全性が高まると考えられる。

「OpenBike」はアクセサリーの取り付けだけでなく、利用も簡単にしてくれる。例えば自転車用ライトであれば、現在は利用者は自転車を降りる度に、次の利用に備えてライトのバッテリーを充電する必要がある。だが、「OpenBike」が導入されれば、ライトだけでなく、サイコンやドラレコなど様々なアクセサリーが充電不要になるのだ。

ペダルを漕ぐことで充電されるが、取り外してAC電源からも充電可能
また、「OpenBike」対応のアクセサリーにはバッテリーを内蔵する必要がなくなるため、サイズが今よりも小さくなると考えられる。ライトなどをポケットに入れて持ち歩く人にとっては、これも大きなメリットとなるはずだ。
将来的には、「OpenBike」では独自の通信プロトコル提供も目指しており、実現すれば別メーカーのガジェット間の通信が可能となる。ここまでくれば、「OpenBike」は自転車用のOSと呼んで良いだろう。たとえば自転車用ドライブレコーダーがサイクルコンピューターのGPSから位置情報を取得。ビデオにその情報を埋め込む、といった利用法が可能になるかもしれない。

Linuxコントリビューターの1人
「OpenBike」の技術が組み込まれた自転車は、2017年に米国MARIN BIKESから登場する予定。通常モデルよりも300ドルの追加で、「OpenBike」対応モデルが手にはいる。この価格で毎日のバッテリーの充電作業から解放されるなら、安いものではないだろうか?
















